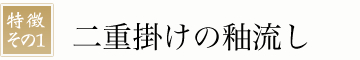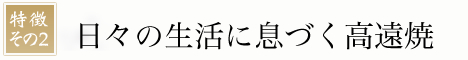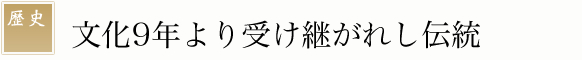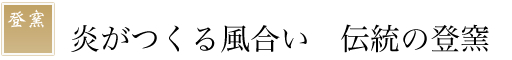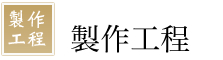高遠焼の特徴は主に釉薬にあります。この地方で採れる粘土は赤土(茶色)だったためか、白い色の釉薬が掛かった上に、緑色の釉薬を流している物が多く、その他の色でも黒色の釉薬の上に白色の釉薬が流してあるなど、釉薬を二重掛けしてあるという所が一番の特徴です。
その他にも、手跡を残したような感じになった形や、口の部分が厚手(全体的に厚手の物も多い)の物も数多く残っています。
作られた物は主に、徳利、甕、鉢などがお庭焼としては多く残され、瓦やタイル、また諏訪、岡谷地方などではお蚕が盛んだったため、繭から糸をとる糸取り鍋も多く焼かれました。
現在では、昔粘土があった場所には家があったり採り切ってしまったなどで粘土があまり採れなくなり、今採れる粘土の耐火度(熱に耐えられる温度)が低いために、高遠で採れた粘土とその粘土に似た粘土とを混ぜて主に使用しています。
釉薬も最近高遠は桜の名所ということもあり、桜をイメージしたピンク色の釉薬ができ、その他にも沢山の釉薬を使っています。
しっかりと焼き上げているため、電子レンジで温めるときにご使用いただいても大丈夫です。ただし直火は割れてしまう恐れがありますのでご使用はおやめください。
また、陶器ですので磁器とは違い、底の部分(裏の部分)に釉薬は掛けてありません。これは粘土を見せるためです。きれいには仕上げてありますが気になる方はマット等敷いてお使いください。
高遠焼は文化9年頃に始められた素朴な焼物です。昭和中頃に衰退しましたが、近年になって見直され、「白山登窯」が築かれ、伝統を受け継いだ高遠焼が復活しました。
高遠焼きは文化9年(1812)月蔵山より高遠城内に水を引くために、美濃国より陶工を招き土管を焼いたのが始まりで、御庭焼となった。
最初窯は花畑の勝間河原に築いた。(現在この窯跡は高遠湖の底に沈む)それ以来幾多移り変わり、その技を受けつぎ、主な原料は当地方の土を使って日用雑器などを焼き、すぐれたものが今も数多く残されています。
この流れを受けた窯屋も、興亡盛衰幾度か替わり、近年まで企業化されるなどして続いておりました。昭和50年2月町営高遠焼として復活しました。益々発展のため、平成7年3月、勝間の白山の地に登り窯を築き、最新の技術と併せて伝統を守り、この地方の味を生かした焼物を作って皆様に親しんで頂く所存でございます。
(左下段は文化十一年に作られた土管)
登窯は高い方へ炎が上る習性を利用し、地面の傾斜を使い窯を築き焼き上げる高遠焼の伝統の窯です。 部屋が何室かあり、一番下に始めに火を付ける部屋、その上の部屋から湯呑や壷などの製品が入っている部屋が何室かあります。
現在高遠焼で使用している登窯は4部屋あります。
薪を使い三昼夜かけて焼き上げ、薪は松材を使用し、一番下の焚口に火を付け、窯の湿気を取りながらじっくりと温度を上げていきます。作品が入っている一つめの部屋(一ノ間)の温度がある程度上がった所で、一ノ間を焼き始めます。温度が低いと薪を入れても燃えずに炭になってしまいます。
一ノ間が焼き上がると、その上の部屋(二ノ間)の温度が上がり、焼き始めます。この作業を繰り返し上の部屋に登っていくように焼くことから登窯と言われています。
現在では、ガス窯、電気窯、灯油窯、等様々な窯がありますが、登窯との違いは、薪の灰が窯内を舞うことによって予想しない色に焼きあがったり、薪のくべ方で温度の差が生じ、一つの作品でも左右で違った発色になることなどがあります。
ガス窯等では安定して焼けるのに対し、登窯では薪の入れ方や焼き方、焼成時間の違いなどでガス窯等では焼けない風合いの作品が出来上がります。
現在高遠焼では灯油窯と併用して登窯を使用しております。
作る前に粘土を練ることから始めます。菊練り(写真1)をします。粘土が菊の花の形のようになることからそう呼びます。粘土を練ることによって硬さを均一にし、粘土の中の空気を抜きます。
粘土を練り終えたら形を作っていきます。電動ロクロ、手びねり等で形を作っています。(写真2)1~2日ほどしてある程度作った物が固くなったら仕上げをして乾燥させます。
乾燥した作品を窯詰め(写真3)、その後素焼きをします。
素焼きした作品に釉薬を掛けます。(写真4)
釉薬が掛かったら窯入れをして本焼をします。(写真5)
本焼をして作品を焼き上げます。登り窯では毎年秋11月初め頃、4昼夜交替で700~1000点の作品を焼き上げます。(写真6)
焼きあがったらゆっくりと冷まして窯出しをします。窯出し後、作品の底の仕上げ等をして完成させます。